兵庫県姫路市の離婚法律相談所 | その他の離婚解決事例集
ご予約・お問い合わせはこちら
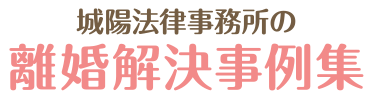
当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。

元々持たれていた財産に、相手方から500万円の支払を受け、800万円弱の財産を確保する形で
離婚調停が成立しました。
上記の通り、800万円弱の財産を確保する内容で財産分与がなされております。
なお、自宅にはローンが残っていますが、自宅の所有者かつローンの債務者である相手方が引き続き
支払を継続する内容となっております(当方は別居しており、自宅を必要としない立場)。
本件、熟年離婚の事案ですが、熟年離婚の場合、若い方の離婚に比べて、
持ち家や住宅ローンがある方が割合的に多く、その取扱が問題となる事が多いです。
本件の場合は、当方は別居を先行しており、自宅を必要としていない事から、相手方が自宅を取得し、
ローンも引き続き支払う内容で問題はなく、相手方もこれを受け容れた事から、この点の問題は生じませんでしたが、
相手方において、「自宅はローン以外に、自分の結婚前からの定期預金も購入費用に充てられているから、その分、夫婦の共有財産として
計上する自宅の価値を低くするべきである」との主張(特有財産の主張)を行ってきました。
この点、特有財産(婚前からの財産であったり、親から相続した財産である等から、夫婦の財産分与の対象価値から除外すべきとの主張)の立証責任は、
特有財産である旨主張する側にあります。そこで、自宅の購入費用に、現に相手方の婚前の定期預金が幾ら充てられたのか、ローンで幾ら借り入れたのか全体が
分かる資料の提出を求めました。
また、結婚から自宅購入までの間にそれなりの年数が経過している事案であった上、相手方が開示した定期預金の通帳では、結婚時に確かに一定の残高があったものの、
結婚後に、生活費に回されたり、逆に収入から定期預金に組み入れた形跡が複数認められたため、「婚姻後の収入が混じっていたり、婚姻後の一家の生活に充てられたりするなどしており、
特有財産性が維持出来ているとは言えないから、自宅の価値全額を財産分与の対象価値として計上すべきである」旨主張し、最終的に、ほぼ当方の考え方に依った場合の金額に近い500万円の支払を受ける形で離婚調停を成立させる事ができました。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。

自宅が夫婦で共有されており、かつ、自宅のローンも夫婦がそれぞれ連帯債務を負っている中、
離婚調停手続中に、第三者への売却を具体的に取り決め、調停成立後に、売却金から諸費用の支払や各自のローンの支払を
行い、残額を夫婦で折半して分ける内容の財産分与の取り決めを行い、離婚調停が成立しました。
上記の通り、自宅の共有関係や負債の問題を解決する形で離婚が成立しました。
離婚を行う際には、合わせて夫婦の財産について財産分与の取り決めを行うのが通常ですが、
財産分与において最も取扱が悩ましい問題として、自宅不動産、ローンの問題があります。
この点、不動産の名義やローンの債務者が夫婦のどちらか一方でかつ、他方が連帯保証等を行っていない場合は、
名義人が引き続き所有し、ローンの支払を行う形で合意を行えば足りる事となります。
対して、本件のように不動産が共有であったり、ローンが連帯債務である場合、離婚時に共有状態を解消しておかなければ、
後々に、別途、共有状態を解消するために交渉や訴訟(共有物分割訴訟)を行う必要があるという問題が生じます。
(共有であるため、他の共有者の同意、協力なくして、一方のみでは不動産を売却できない。理論的には自分の共有持ち分だけなら自分だけで売却できるが、買い手が共有を嫌い、買い手は通常つかない。共有者が協力しない場合、共有状態を解消する手段として共有物分割訴訟があるが、解決方法は、どちらかが100%取得する代わりにローンも全て支払うか、手続外で任意売却を行うか、手続内で
競売を行うかのどれかとなるため、それであれば、離婚時の財産分与の段階で、任意売却の道筋を立てておいた方がよい事となる。)
本件では、不動産を売却して各自のローンの支払に充てる旨の提案を離婚調停内で行ったところ、相手方も了解した事から、
不動産業者に査定を取得し、売却予定額について相手方の了解を得た上で(双方の負債が完済できる内容)、売却先を不動産業者に探してもらい、
売却予定日や司法書士の費用その他も確定した上で、離婚調停を成立させ、その後、売却を実行し、諸費用やローンの支払を行った残額を折半で分けております。
なお、このような進め方の場合、売却には種々の書類の取り交わし(契約書は元より、登記手続に必要な書類等)が必要となりますが、実際に交付してくれるのか
不明であるため、リスクを低下させる観点から、事実上、調停成立より先行して、相手方が署名、押印した種々の書類を依頼した司法書士が預かった事が確認できた状態で調停を成立させ
ております。
また、調停手続中に売却について具体的に取り決める際の注意点として、例えば売却金額についてなかなか折り合いがつかない等の事態になると、
裁判所が「それであれば、売却金額や売却先が具体的に決まってから再度、調停を申し立てるなりする事とし、一旦、調停を取り下げるべきではないか」
と述べてくる可能性が生じるため(離婚調停の期日を何期日も待ってくれない可能性)、出来るだけ早期に最低売却価格を取り決めると共に、売却先を確定する必要があります。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決を図ります。

離婚原因が認め難い中、相手方から離婚を求められたのに対し、当方から婚姻費用分担調停を申し立て、
相手方から離婚調停が申し立てられ、婚姻費用、解決金合わせて600万円弱の金員を得る形で離婚調停が成立しました。
本件は、婚姻を行ったものの、同居を行った事がなく、婚姻からそれほど期間がたたない中で
離婚を求められた事案であり、財産分与は期待しづらいという状態にありました。
相手方は、同居しなかった等と述べ、離婚原因が存在する等と主張したのに対し、当方は、同居しなかったのではなく、
同居のための住居等を適切に相手方が確保する等の対応を行わなかったり、双方の考え方の違いによるものであり、
当方に帰責性がある訳ではない旨、主張し、その上で、離婚を求めるのであれば、未払婚姻費用は当然であるが、これとは
別に一定の解決金の支払がなされれば、誠意が見せられたものとして、離婚に応じる事も考え得るとのスタンスをとりました。
結果、婚姻費用、解決金合わせて600万円弱の金員を得る形で離婚調停が成立しました。
離婚を相手方から求められた場合の対応としては、
①離婚に応じる、②離婚には一切応じない、の他、③条件次第では離婚に応じるという方法が考えられます。
本件では、当方に不貞行為や暴力等の有責性は認められず、その他、同居に至らなかった経緯についても当方に帰責性が認められるものでは
ないと考えられた一方、相手方が弁護士を代理人に立て、調停まで申し立ててきた事等に鑑みると、関係の改善を図り、夫婦生活を営んでいくことは
事実上困難であると考えられ、離婚には全く納得がいっていない。何らかの条件が提示された場合、検討は行う。というスタンスをとりました。
このような場合、解決金についてはどのように考えるべきでしょうか。例えば、不貞行為が認められる等の場合は、慰謝料の問題となり、
訴訟に至って判決が出た場合の離婚慰謝料には一定の相場があるとされているため、これをベースに考えることができます。
対して、本来、離婚するだけの事情(法律上の離婚原因)が認められないにもかかわらず、離婚に応じる、という解決金は、慰謝料と異なり、
法的な請求権ではないため、「判決での相場」というものがありません。
このような場合、現時点で離婚が成立した場合と、離婚が成立せず、別居期間をある程度確保された段階で離婚が成立する場合を比較することが
実務上、行われています。すなわち、離婚が成立するまでの生活費は、婚姻費用であり、配偶者の生活費(+子の生活費(養育費))を支払う必要があります。
対して、離婚が成立した場合は、お子様がおられる場合は養育費、そうでない場合は、生活費は不発生となります(離婚により、配偶者に対する扶養義務が無くなるため。)。
法律上の離婚原因が認め難い場合、別居期間に着目することが多いですが、一般的には3~5年程度と説明されることが多いです。
3~5年程度の期間(正確には、別居してから現在までの期間分は差し引く必要。ただし、その部分は、婚姻費用調停を申し立てている場合等は、婚姻費用として計上することとなります。)、婚姻費用を払い続ける場合と、現段階で離婚を成立させ、3~5年程度養育費を払い続ける場合(子がいない場合は、0円)の差をもって、解決金の目安とすることが考えられます。
本件では、相手方が少額の解決金の提案を当初行っていましたが、当方は、離婚訴訟において、法律上の離婚原因が認められにくい場合の裁判所の和解案として、
上記のような運用を採られていることから、婚姻費用額の5年程度の金額が提示されて然るべき旨、主張し、相手方は3年程度の金額を提示してきた事から、当方は4年程度の
金額を提示したものの、相手方が応じなかったため、裁判所(調停委員会)に解決案の提示を求めたところ、上記の通り、
こちらの考え方に沿う形で解決案が提示され、双方合意に達する事ができました。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決を図ります。

熟年ご夫婦の離婚事件で、財産分与として約2800万円の財産を当方が取得する形で離婚調停が成立しました。
上記の通り、財産分与として約2800万円の財産を当方が取得する形で、離婚調停が成立しました。
その他、年金分割についても通常どおり按分割合を0.5と定めており、これによりご離婚後の生活についても
安定した生活が期待出来るかと思われます。
本件の特徴は、夫が自身の給与等を管理し、依頼者様である奥様側は月々わずかの生活費しか渡されておらず、
夫側の財産の全容が不明である点にありました。
そこで、示談交渉ではなく裁判所での調停手続を選択の上、調停手続内で資料開示を相手方に行っていただき、
存在しないものは存在しない旨、書面等裁判所の記録に残る形で回答を行っていただくこととしました。
これにより、意図的に、存在しない、などと回答を行ってくる事態を少しでも防ぐ事を想定しております。
財産の資料の開示を求める際には、単に「財産の資料を開示されたい」とするのではなく、個別に財産(例えば、預金、生命保険、退職金など)を挙げ、
回答の漏れを無くす事が重要です(いつの分が必要なのかも明示する事も重要です。別居時等ある一時点の履歴等しか開示して来ない事も考えられるためです。)。
また、特有財産の主張を行うものについては、財産分与の対象ではないから、開示しなかった、などと述べてくる可能性もあるため、
特有財産の主張を行うか否かに拘わらず開示を求めることも重要です(そもそも特有財産に当たるのかや、裏付け資料があるのかが問題となるため、その判断を相手方のみに
委ねて資料開示を求める事になってしまうためです。)。
また、相手方の退職金の取扱につき、争いが生じたものの、
相手方の定年退職時期が間近いため(1年程度後)、退職金が支払われる蓋然性が高いことから、
自己都合退職による金額をベースにするのではなく、定年時に定年退職された場合の金額をベースに、定年までの分及び婚姻までの分を控除する
形を採るべき旨主張し、これに基づき算定された金額を財産分与の対象価値の価値と考えることとなりました。
(自己都合退職の場合の金額よりも定年退職した場合の金額の方が通常は大きい事が多いです。)。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。

1500万円程度の財産を財産分与として確保した他、約300万円程度の慰謝料等の支払を受ける形で離婚調停が成立しました。
相手方が、当初、離婚調停を申し立てたのに対し、当方が慰謝料の請求や有責配偶者からの離婚請求である旨の
主張を行い、解決金の支払いを求めたところ、相手方が調停を取下げたため、当方が離婚調停を申し立てたところ、
数回で不出頭を行うようになり、訴訟提起を経たところ、出頭するようになり、再度、調停で話し合いを行った結果、
上記のとおり調停成立にいたりました。
本件では、自宅不動産やローンの名義が相手方名義であったところ、当方が財産分与で自宅不動産を取得したいとの希望が
あったため、訴訟での解決ではなく、調停等の話し合いで解決を行う必要性が高い事件でした。
幸い、訴訟提起後に、相手方が出頭するようになったため、当該調停手続内で、一挙解決を図ることを目指しました。
相手方名義のローンの借換を当方で行う必要がありましたが、その一方で、相手方が財産分与その他の支払を、確実に
当方に行ってもらう必要があり、その原資を現実に確保してもらった事が確認できた状態で調停を成立させるなど、工夫を
要するところでした。
このように、離婚に伴い、自宅やローンの名義を変える必要がある事件では、工夫を要します。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決を考えます。

財産分与として、2000万円弱の財産を取得する事とした他、
養育費として月40万円弱の支払を受ける形で離婚調停が成立しました。
相手方は、自身の収入が婚姻費用の算定表上の上限を超えていることから、
相手方の収入はこれより上であっても、上限の範囲とすべき旨、主張していましたが、
これに対し反論を行い、結果、算定表の上限に限定されず、婚姻費用の支払を行っていただく事ができました。
婚姻費用、養育費を定めるに際しては、裁判所が作成した、「算定表」に当てはめて
月額が考えられることが裁判実務上、多いことは、ご存知の方も多いかと思われます。
ところで、当該算定表では、給与所得者の場合、2000万円、事業者の場合、1567万円までの表となっており、
夫婦のいずれかの収入がこれを上回る場合に、上記金額に限定して考えるべきではないかが論点となる場合があります。
この点については、様々な考え方がありますが、婚姻費用と養育費では考え方を分けることが考えられます。
すなわち、婚姻費用については、夫婦双方の収入に応じて、生活費を考える事となり、収入の多い方が、自身の収入を前提とした
自身と同様の生活を相手方にさせる義務を負うこととなるため、収入が多ければ、それだけ相手方に払うべき金額も多くなるのではないか、
との説明が考えられます。
対して、養育費については、教育費には自ずと限界があると考えられることから、収入についても、限界があるのではないか、との説明が
考えられます。
離婚について弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所までえん
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。

別居以降もペットを当方が育てているものの、購入代金のローンは
相手方が債務者となって支払っている事案につき、
離婚成立後も、ペットは当方が所有し、ローンは相手方が負担する形で
離婚調停が成立しました。
ペットの取得希望を当方が述べたのに対し、
当初、相手方は、それであれば、ペットのローンも当方で支払うべきである旨、
主張していましたが、交渉により、ペットは当方が取得しつつも、ローンは相手方が離婚後も
引き続き支払い続ける形で離婚調停が成立しました。
ペットも、民法上は「動産」であることから、財産分与の対象に理論上はなり得ることと
なります。
もっとも、財産分与は、経済的な価値のある(=時価のある)財産をどう分け合うか否かが問題となり、
経済的に無価値なものについては、当事者間で協議して分けることはできても、離婚訴訟に付随して財産分与の判決を取得する場合や
財産分与の審判においては、判断の対象に含まれないと考えられるのが通常です。
この点、ペットは、購入した段階では時価が存在することとなりますが、購入した後は、通常は、時価がつかない(転売できない)事と
なり、合意しない限り、財産分与の対象とはならないのではないか、という問題が考えられます。
また、通常は、ローンの対象となる財産を取得する者が、離婚後のローンの支払を行う事となります
(例えば、夫婦の自宅を財産分与で取得する側が、自宅に残ったローンを負担する(あるいは借り換える)など。)。
しかし、「ペットは無価値であるから、離婚時の財産分与の
対象財産とはならない」との主張を排斥し、ペットを夫婦の共有とした上で、財産分与の扶養的要素を考慮し、定期金として、
月々、飼育費用の一部の支払を命じる福岡家裁久留米支部令和2年9月24日判決が近時、出されています。
(飼育費用として、月々のペット代の他、ペットを飼うために賃借を余儀なくされた
(当該事案は、犬3匹を一方が飼育することとなる事案でした。)家の賃料の一部が計上され、これを割合的に一部、ペットを飼育しない側に
負担させるものです。)。
ペットを財産分与で当方が取得したいと述べたのに対し、前述の通り、相手方は、ローンも当方で負担すべき旨、主張しました。
これに対し、当方は、当該裁判例を調停に提出し、ローンを当方が支払うのであれば、飼育費用を相手方が負担すべき旨、主張しました。
その上で、実際には相手方が飼育費用の月々支払う形を採ることは、離婚後も、相手方との関係が残ることとなり、双方にとって負担が大きいことから、
ローンを相手方が負担するのであれば、飼育費用を相手方が負担すべき旨の主張は撤回する旨、述べ、
最終的に、相手方もこれに応諾し、上記の通り、離婚調停が成立しました。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。

婚姻期間が短く、めぼしい財産がない中、400万円の解決金の支払を受け、
養育費月17万円の支払を受ける内容で、離婚調停が成立しました。
別居がいつから始まったか及び、別居に至る原因、経過等について双方に
争いがある中、当方は、一定の解決金の支払を受けなければ、離婚に応じることが
できない旨、示しました。
当初、相手方は、100万円程度の解決金しか提示しませんでしたが、交渉の結果、
400万円の解決金の支払を一括で受けることができました。
これとは別に、養育費月17万円の支払を20歳まで受ける事を内容とする他、
離婚成立までの婚姻費用についても、子の出産費用の半額の支払を受け、かつ、月29万円の婚姻費用の
支払を受ける形で合意に至りました。
離婚が認められるには、夫婦双方が合意するか、一方が同意しない場合は、
法律上の離婚原因が必要となることは、ご存知の方も多いかと思われます。
本件では、夫婦双方に、暴力や不貞行為などの事情が認められないため、
主に、別居期間が離婚原因として重要な意味を持つと考えられました。
当方としては、暴力等の帰責事由がみとめられない以上、5年程度の別居期間が必要として、
離婚を早期に成立させる事で、相手方は、婚姻費用から子の生活費である養育費に月々の支払が下がる点を捉えて、
5年分の婚姻費用と養育費の差額の支払いを解決金として行うべき旨、主張しました。
最終的には、約4年分の差額である400万円の支払を受けることが可能となりました。
その他、別居中に、当方が出産に至ったことから、出産費用の半額の負担の支払を受け、
また、出産以降は、子を1人監護していることを前提とした婚姻費用と考えるべき旨、主張し、月29万円の婚姻費用の
支払を受けることができました。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。

財産分与として1500万円程度の財産を取得する形で離婚調停が成立しました。
一部の財産に、特有財産が原資となった財産が存在したことから、
原資の立証を行い、財産分与の対象から外す等の調整を行い、最終的に前記のとおり、
離婚調停が成立いたしました。
離婚の際の財産分与においては、夫婦名義の財産は、夫婦共有財産との推定が働くことが
多いです。
推定が働かない場合としては、婚姻後に夫婦の収入に比して直ちに大きな金額の財産が存在しているなどの場合が考えられますが、
そうでない場合は、当該財産の原資が婚姻前からの預貯金等であるか、親から贈与、相続等で取得した預貯金等であることを
金銭の流れが分かる形で立証する必要があります。(金銭の流れが立証できなければ、元々の原資との同一性が立証できないこととなってしまいます。)
本件では、通帳上、相続で金員を取得したことが明らかであり、これを原資に購入したことも
通帳上、明らかであることから、立証に達し、財産分与の対象から外すことができました。
なお、このように、原資の立証及び原資との同一性の立証ができない場合でも、近時は、特有財産の規模によっては、
「一切の事情」として財産分与で調整を図る(特有財産分の金額をそのまま引くのではなく、その何割かを差し引く)
高等裁判所の裁判例も登場しているところです(東京高裁決定令和4年3月25日)。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりを考えます。

簡易な解決として、夫婦それぞれが保有する財産をそれぞれが取得することとして、調整を行わず、
これとは別に、当方が親から相続した自宅土地について、相手方が時価相当額(500万円)で一括で買い取る内容の
離婚調停が成立しました。
上記の通り、500万円の支払を受ける形で、離婚調停が成立しました。
相手方に代理人がついておらず、本人のみであったことから、500万円の支払を確実に受けられるよう、
離婚調停の席上で、500万円の交付を受ける形で調整し、離婚調停成立の日に、500万円全額の支払を受け、
合わせて離婚調停成立となりました。
方向性として、①夫婦双方、財産の資料を開示し合い、それぞれいくらずつ夫婦財産を有しているのか
厳密に特定した上で、財産分与額を決めるという方法も考えられるところでした。
しかし、本件では、婚姻後、当方が親から贈与を受けた金員が複数回、それなりの額存在することから、
これを特有財産として、財産分与の対象から外れる旨、主張する必要があったところ、特有財産であることの
立証は、特有財産であるとの主張を行う側に課されており、かなり古い年月のものであることから、金員の流れについて
客観的な資料の提出ができず、特有財産の立証が難しい点が懸念されました。
そこで、依頼者の方と協議した結果、簡易な解決として、夫婦それぞれが、各自保有する財産を持ち続けることとし、これとは別に、
親から相続した自宅土地について、相手方が時価相当額500万円で一括で買い取る内容で解決可能であれば、
当該内容で離婚調停をまとめる用意がある旨、調停で述べたところ、相手方も最終的にこれに応じ、早期解決を
図ることができました。
このように、離婚訴訟と異なり、離婚調停においては、簡易な解決を図ることも場合により可能であり、
自身の主張、立証の有利不利を踏まえて、不利な点を補うために簡易な解決を目指すことも、戦略的には有効となる場合が
あります。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。