兵庫県姫路市の離婚法律相談所 | 婚姻費用に関する離婚解決事例集
ご予約・お問い合わせはこちら
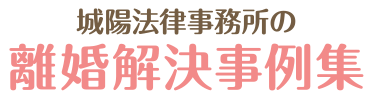
当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。

相手方が、当方の不貞行為を理由に、相手方名義の不動産からの退去を求めて訴訟提起したのに対し、
当方が必要な反論を行ったところ、裁判官の見解が訴訟内で示され、相手方の訴え取り下げにより
訴訟が終了しました。
上記の通り、相手方が訴えを取り下げ、引き続き当方が自宅に住み続けることができるように
なりました。
相手方は、当方が不貞行為を行ったとして、当方が相手方名義の不動産に住み続けることは、
婚姻関係が継続していたとしても、信義則違反ないし権利濫用等により認められない、などとして
相手方名義の建物からの退去を求めて訴訟提起を行ってきました。
当方は不貞行為の存在自体を否認しており、その点も問題となるのですが(別件の婚姻費用の審判においても、不貞行為の存在が否定されました。)、それ以前の問題として、
本件不動産は、結婚後にローンを組んで購入されたものであり、婚姻中の夫婦の収入から支払がなされたものであり、
夫婦の共有財産であり、登記簿上、相手方単独所有になっていたとしても、夫婦の共有に属し、所有権(共有持ち分権)を有しており、
仮に不貞行為の存在が認められる事案であったとしても、自分の所有物に住んでいることになるため、信義則違反や権利濫用の問題が生じる余地は
ない旨、答弁書で、過去の裁判例なども証拠提出して反論しました。
また、上記の通り考えられるため、不貞行為の存否について主張、証拠の整理を行ったところで、結論に影響しないと考えられることから、
法的見解、解釈に属する事項であるため、裁判官において、早期に、夫婦の共有物であるという事であれば、請求は棄却され、不貞行為の有無が問題と
ならない旨、見解を示していただくことが、訴訟経済に資する旨、進行について意見を述べました。
結果、裁判官から、「夫婦共有財産という事であれば、相手方の単独所有が否定されるため、相手方の請求は棄却されることとなる」旨、
法的見解が示されました。
合わせて、当方から、婚姻費用分担審判において、相手方が当方居住の自宅のローンを支払っていることを踏まえて、当方の収入に応じた統計上の
居住関係費を差し引いて婚姻費用額が定めらていることから、賃料相当額の請求を相手方請求している点にも理由がない旨、主張しました。
結果、相手方は訴えを取り下げ、当該訴訟は終了しました。
確かに、①不動産が婚姻前から夫婦の一方が有していたものであり、かつ、ローン等の支払も婚姻前に終わっているとか、②夫婦の一方がその親から相続した不動産である
などの場合には、夫婦共有財産とは言えないこととなるため、不貞行為が認められるケースにおいては、使用貸借権ないし夫婦の同居義務に基づく居住権を主張することは、
信義則違反ないし権利濫用に判断されると判断される可能性がありますが、夫婦共有財産の場合に当てはまる議論ではない点に注意が必要です(弁護士ですら、この点を誤解していると思われると感じることが時折あります。)。
離婚問題について、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。

婚姻費用分担審判において、第1審が、当方のLINEのやりとりから不貞行為や暴行を認定し、本来の額よりも
減額した金額(子の養育費相当額のみの金額)での請求しか認めなかったのに対し、即時抗告を行い、第2審において、不貞行為や暴行を認定することは
できない旨、判示され、当方本人分の生活費も含めた婚姻費用の請求が認められました。
上記の通り、不貞行為、暴行の認定に問題があったことから、これを不服として即時抗告を行ったところ、
当方の主張が認められ、不貞行為や暴行の存在が否定されました。
婚姻費用(別居中の離婚までの間の生活費)の請求においては、不貞行為や暴力など、別居に至る原因がもっぱら
請求を行う権利者側にある場合、権利濫用ないし信義則違反により、子の養育費部分は別として、自身の生活費部分を含めて
婚姻費用を請求することはできない、と考えるのが離婚実務の通例です。
本件では、相手方は、別の男性との間のLINEや、切り刻まれたとするシャツの写真を証拠として提出し、それぞれ
不貞行為や身体に向けられた暴行があったとして、当方の婚姻費用の請求が権利濫用に当たる旨、主張していました。
1審では、LINEのやりとりが、男女のやり取りであるなどとして、不貞行為の存在を認め、これとは別に、暴行の存在も
認めました。
しかし、当該LINEは、ある1日のみのやり取りであり、実際に会ったり肉体関係をもったことをうかがわせるやり取りなどは
全く含んでいないものであり、当方の主張(弁解)にも符号するものでした。
当方は、この点を指摘し、当方の主張にも符号する証拠であり、また、当方の主張がおよそあり得ないものである等と
排斥できる関係にもないこと(むしろ、一定の具体性、まとまりのある弁解であり、信用性が認められること)、
当該LINEのやり取りが発覚してからも、夫婦関係は数年にわたり継続してきたものであり、当方の当時の説明により
相手方も納得したものであるという当方の主張にも符号すること、実際、調停においても、当初、離婚の原因は暴行の点にある旨、相手方は主張し、不貞行為を理由とは
していなかったことなどから、不貞行為は認められない旨、主張しました。
また、暴行についても、暴行の存在を否認しているにもかかわらず、もっぱら相手方の供述のみで暴行の存在を認めている原審の判断には
根拠が乏しい旨、主張しました。
結果、高等裁判所では、不貞行為、暴行、いずれの存在も否定され、当方本人分の生活費も含めた婚姻費用の請求が認められました。
婚姻費用における不貞行為、暴行の認定と離婚請求における不貞行為、暴行の認定は、別手続であることから、
理論上は必ず同じ結論になる必要はない事ととなりますが、
実際上は、同じ主張、同じ証拠であれば、異なる判断にはしづらくなるものと考えられ、離婚請求の際にも影響を与え得る重要な争点に関する判断であったと言えます。
離婚問題を弁護士に相談、依頼をお考えの方は姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。

相手方に不貞行為が存在する中、養育費として月々16万5000円の支払を受け、
これとは別に、解決金として700万円の支払を受ける内容で離婚審判(調停に代わる審判)が確定しました。
相手方は、当初、不貞行為を否認していましたが、離婚調停の中で、
不貞行為の主張、立証を具体的に行ったところ、不貞行為の存在を認めるに至りました。
その上で、慰謝料及び解決金の額を幾らにするかについて、調整を行ったところ、
相手方は当初、200万円の解決金の提示を行ってきましたが、交渉の結果、700万円の支払を
3回払いの短期間の分割で受ける内容で合意に達しました。
裁判所が遠方のため、調停を成立させるには当事者双方が裁判所に出頭の必要があることから、
調停に代わる審判を裁判官に行っていただき、双方、不服申立権の放棄を行い、確定させる形を取りました。
これに加え、月額16万5000円の養育費の支払を受ける内容とすることができました。
不貞行為を行った側から離婚調停を申し立てた場合、申し立てられた側の対応としては、
離婚の条件として、慰謝料、財産分与はもちろんの事、解決金の支払を求める事が多いかと
思われます。
この点は、離婚する事により、婚姻費用(配偶者の生活費を含んだ生活費)が養育費(子のみの生活費)に下がるという経済的利益を
相手方は受けることとなるところ、離婚を行うには、特に落ち度がない事案では5年程度の別居、離婚を求める側に不貞行為が存在する事案では、
相当長期間の別居(7~10年程度)及び未成熟の子がいないこと(経済的に独立して然るべき年齢(20歳程度)に達していない子がいないこと)が
要件となり、このような長期の年数×(婚姻費用と養育費の差額)分、支出を免れる点を捉えて、解決金を求めることが考えられます。
本件では、不貞行為を相手方が行ったものの、相手方が具体的な解決を示さないことから、離婚調停の申立て自体は、当方から行いました。
ただし、「不貞行為を行ったのは相手方であり、元々、相手方から離婚を求めたところ、相手方が具体的な中身を話さないことから、
やむを得ず、当方から離婚調停を申し立てたものであり、条件が誠意あるものでなければ、取下げを行う考えである」という条件付きでの申立てを
行っております。
不貞行為を受けた側から離婚調停を申し立てるのは不利ではないか、との考え方もありますが、本件では、相手方の不貞行為の確実な証拠があった事から、
どちらにしろ、相手方から離婚訴訟等を起こしてきて、破綻等の主張を行ったとしても、有責配偶者からの離婚請求に当たると判断される見通しであったことから、
上記のような条件付きの離婚調停を当方から申し立ててもリスクが少なく、早急に離婚を成立させたいとの依頼者の方のご意思からすると、相手方からの離婚調停を
待っても、いつになるか分からないことから、条件付きの申立てを当方から行うことをご提案し、そのように進めることとなったものです。
相手方は、当初は、このような解決金を求める法的根拠はない旨、主張していましたが、複数回の協議の結果、700万円の解決金を行う形で
合意に達し、その内容で調停に代わる審判を受け、これを確定させることができました。
(なお、財産分与については、相手方には住宅ローンが存在し、求めても、ほとんどプラスにならないか、むしろマイナスとの見立てを依頼者の方が
行っておられた事から、方針決定の際、財産分与をこちらからは求めない事としております。従って、相手方から金額を確保するには、慰謝料、解決金で支払を受ける
必要があった事案という事になります。)
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。

子の私立高校の授業料、通学定期代、諸会費などの加算を含め、月額19万円弱の婚姻費用の支払いを受ける形での
調停が成立しました。
当方の請求通り、裁判所も支払の必要性を認め、相手方もこれに応じて、婚姻費用分担調停が成立しました。
調停成立までの間の未払婚姻費用も、一括で支払を受ける内容となりました。
月額19万円弱の婚姻費用を月々、確保できた事により、本体の離婚調停についても、焦らず時間をかけて解決できる事となり、
また、相手方にも、経済的負担がかかる事から、早期に条件を整えて、離婚を成立させる動機が働くこととなり、
婚姻費用にとどまらず、離婚の条件交渉においても有利な立場に立つ事ができたと言えます。
本件は、私立高校の学費による加算が問題となった事案です。
公立高校と異なり、私立高校の授業料等は高額に及ぶことから、離婚成立までの間の婚姻費用の分担請求において、
夫婦双方の収入、子の数、年齢に基づく、いわゆる算定表による基本月額に加えて、加算を求めることができるかが
問題となります。
本件では、別居開始前から私立高校に通学していたので、相手方が私立高校への進学を了承していた事が
推認できる関係にありました。
また、学費加算を求める場合、授業料以外の費用の加算が認められるかが問題となりますが、合理的な経路による電車、バス等の通学費用は
加算の対象に含まれるものと考えられますし、諸会費等、学校に在籍する事により当然に発生する費用なども加算の対象に含まれるものと
考えられ、本件も同様の解決を図ることができました。
なお、学費加算が認められる場合でも、全額の負担を相手に求めることができる訳ではなく、
算定表に考慮済みである、公立高校(ないし公立中学)の年間標準額費を上回る部分を、夫婦双方の収入で按分した額の加算となります。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。

相手方の種々の主張を排斥し、当方の主張通り、月額15万円に3万3600円の加算(高校授業料、定期代等)した内容で
婚姻費用調停が成立しました。
相手方は、①種々の費用を払っており、既払金に当たる、②子の授業料に充てるため50万円を当方が保有しており、
これを子の授業料等による特別の経費加算に充てるべきである、など種々の主張を行っていたのに対し、
これらを排斥し、当方の主張どおり、高校授業料、定期代等の特別の経費加算も含め、月18万3600円の婚姻費用の支払が必要との
裁判所の意見を得た上で、当該内容で婚姻費用分担調停をまとめる事ができました。
離婚までの間の生活費である、婚姻費用分担調停や審判において、既払金の主張がなされる事があります。
しかし、よくある問題として、①支払自体は、別居以降になされているものの、その内容は同居中に発生した費用まで、婚姻費用の既払金にされている。
②支払自体は別居以降になされているし、費用が発生したのも別居以降だが、離婚時の財産分与で調整すべき費用まで婚姻費用の既払金にされている。
という事があります。
本件でも、当方の車の修理費用を、相手方が別居以降に負担している、などと主張していましたが、修理自体は同居中に行っているため、婚姻費用の既払金には含まれない旨、
主張しました。その他、携帯利用料等についても、同様の問題があり、同じく、含まれない旨、主張しました。
また、当方が利用している車の任意保険の費用を、相手方が払っている点についても、離婚の際の財産分与で調整すべきものであり、婚姻費用分担調停の既払金には
含まれない旨、主張しました。
その他、大学生の子の授業料を相手方が払っている旨、相手方は主張していましたが、当方も半期分の授業料を負担していること、子はアルバイト収入で
自らの家賃や生活費を得ている事などから、大学生の子については、夫婦のどちらも監護していないものとみて、既払金には含められない旨、主張しました。
結果、裁判所も当方の考え通りの心証を形成し、調停委員会の意見として相手方に伝えられ、結果、当方の主張通り、月18万3600円の婚姻費用で調停が成立するに
至りました。
このように、婚姻費用の調停、審判では、細かな既払金等や、子をどちらが面倒を見ていると考えるのか等について主張がなされる事がありますが、
適切に主張、立証を行い、裁判所に正しい心証を得ていただく事が重要であり、弁護士に依頼される有効性の1つが認められるかと考えられます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。

相手方の年収が0円であるところ、相手方は、緑内障による視野障害を理由に、稼働できないとして、無収入である事を前提に婚姻費用を決めるべき旨、
主張したのに対し、当方は、働く能力を有していないとは認められず、働けるのに働かず、当方の収入に依存しているに過ぎず、相手方には推定収入の考え方を
用いて、従前に働いていた頃の約350万円程度の収入は得られるものと見て婚姻費用を算定すべき旨、主張したところ、
裁判所は、少なくとも年200万円程度の収入が得られるものと見て婚姻費用を算定すべき旨、審判を行いました。
審判においては、「診断書によれば、重い荷物を持つ仕事や不潔な環境で作業を行う仕事は
失明の危険があり、また、職業運転手としての業務は視野障害当により不適当であるものの、これらの作業を伴わない
仕事であれば就労が可能であることが認められる。そうすると、相手方は、就労が可能であるのに就労していないものと
認めざるを得ない。そして、相手方が従前、約350万円ないし400万円の収入を得ていたことを考慮すると、相手方には
少なくとも年間200万円程度の収入が得られるだけの稼働能力があるものと認められるから、これを前提に婚姻費用分担金を
算定する。」と裁判所が判断しました。
離婚までの間の別居中の生活費である婚姻費用や離婚後の子の養育費を
決める際は、夫婦の収入額が結論に影響します。
今回の場合、相手方はここ10年ほど緑内障を理由に働かず、当方の収入に依存して生活してきたという
事情がありました(当方は離婚原因としても主張を行っているところです。)。
相手方は、緑内障による視野障害から働きたくても働けないので、収入は0円でと考えるべき旨、主張しました。
これに対し、当方は、稼働できない等と主張している一方で、冬季に子を連れてスキーに出かけたり(移動は車)、
1人で北陸まで車で旅行に出かけるなどしている事を、相手方と子の間のLINE等を証拠として提出して主張しました。
また、相手方は最終的に医師の診断書も証拠として提出してきましたが、その中身を見ても、一定の注意は必要であることが
窺えるものの、およそ如何なる仕事も出来ないとの事情までは認められないため、この点を主張しました。
その上で、10年程度以前の収入は約350万円程度であった事から、当方は、これを前提に相手方の収入を考えるべき旨、主張しました。
結果、裁判所は相手方の稼働能力を認めた上で、少なくとも約200万円の収入が得られると見るものとなりました。
婚姻費用で争っている際に、自己に有利な結論となるよう、意図的に仕事を辞めたケースであれば、従前の収入と変わっていない前提で婚姻費用や養育費を定めるケースも
ありますが、今回の場合は、そこまでの事情は認められず、また、収入を得ていたのが10年程度前の事であることから、10年程度前の年収そのものを用いる事までは
難しいかと思われましたが、裁判所はバランスを取って、通常の専業主婦の方の場合に裁判所が用いる推定収入年収100万円ないし120,130万円程度(一般的なパート収入)という枠組みを越えて、
200万円程度は得られると認定したものであり、この点で一歩進んだ判断を行っていると考えられます。
このように、現実に無収入であったとしても、推定収入の考え方を採用し、一定の収入を得る力がある事を前提に
婚姻費用や養育費を定めるケースが存在するため、調停や審判、訴訟においては、適切な主張、立証を行う必要があります。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。

離婚に伴う財産分与の分与割合を当方65:相手方35とする形での
財産分与を内容とする、調停に代わる審判を得て、離婚が成立しました。
本件では、①当方の婚姻前からの保有財産が相当、混在していたこと、
②当方の前配偶者からの養育費の支払や、当方の婚姻前からの稼働に基づく退職金の入金等も
夫婦財産の形成に一定程度、寄与していることがうかがわれること、
③実質的婚姻期間が比較的短期間にとどまること、
④当事者の収入、家計状況
等を踏まえると、離婚に伴う財産分与による分与割合の修正が必要な事案であると裁判官が判断し、
具体的には、当方65:相手方35の割合で夫婦の財産の分与を行うべき旨、解決案が示され、
これに双方が内諾を示したことから、調停に代わる審判が出され、確定した事により、離婚が成立しました。
これにより、当方の手許に3000万円以上の財産を残すことができました。
離婚時の財産分与においては、分与割合は原則として50:50と
考えられています。これは、どちらかが専業主夫、主婦であったとしても同様です。
しかし、事案によっては、夫婦間の収入格差が大きく、修正が必要な場合があります。
(本件では当方が2000万円弱の年収に対し、相手方は900万円程度。また、婚姻前からの預金等が相当、混在。)
そこで、本件では年収差や、婚姻前からの預金の存在、混入や前配偶者からの養育費の入金等を立証し、
第1段階としては、婚姻前からの財産については、財産分与の基準時(別居開始時)における残高から差し引くべきとの主張を
行いました。
ただし、このような控除が認められるのは、通常は、婚姻前からの財産に婚姻後の収入が混在していない場合と考えられているところ、
本件では、婚姻前からの普通預金に、婚姻前からの稼働による退職金や婚姻後の給与等が婚姻後に振り込まれているなど、混在が多数見られていたため、
特有財産として差し引くことが難しいことが予想されました。
そこで、第2段階の主張として、仮に、特有財産による控除が認められなかったとしても、財産分与の基準時現在における残高がこれほど高額に
形成できている理由が、当方の収入が大きい事や、婚姻前からの財産の混入によるものである事から、分与割合を当方が大幅に多くなるよう修正すべきである旨、
主張しました。
結果、裁判所も第2段階の主張を認め、分与割合を当方65:相手方35とする内容での解決案を示し、これに基づき離婚が成立するに至りました。
なお、これまでの裁判例を見る限り、分与割合を修正するとしても、70:30程度までが限界とされているようであり(この点は裁判官の解決案にも記されているところでした。)、
本件では限界にほぼ近い形での解決を図ることができました。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。

250万円の解決金を得る形で早期に協議離婚が成立しました。
本件は、婚姻期間が短く、財産分与として分け合う財産に乏しい事案でした。
他方で、当方は結婚以前に仕事を辞めており、離婚して再スタートを切るにも、
財産にとぼしい状態でした。
そこで、別居を行った上で、当職に協議離婚を依頼され、
当方からは、相手方に対し、300万円の解決金を支払う形での協議離婚を提案しました。
交渉の結果、250万円を一括で支払っていただく事を条件として、協議離婚を成立させることが
できました。
本件では、相手方に不貞行為や暴力等の明確な法律上の離婚原因はなく、
当方としては話し合いで離婚をまとめる必要がありました。
また、相手方に不貞行為等がないため、慰謝料の請求を行うことができず、また、婚姻期間が短いため、財産分与の対象となる財産にもとぼしく、
法的に請求が困難な側面がありましたが、本件では交渉の結果、まとまった解決金を得ることができ、
依頼者の再スタートの資金を確保することができました。
財産分与も慰謝料も請求が困難な場合、相手方からまとまった解決金の支払を得ることは、法的な請求権がないため、
交渉が難しいところであり、弁護士に依頼される必要性が高いものと考えられます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。

当方に不貞行為が存在するように評価されやすい不利な事実がある中、
財産分与の金額に30万円程度上乗せした金額の解決金を支払う内容で、
裁判上の和解離婚を成立させることができました。
当方には、別居後、異性の家を間借りしているという不利な事実がありました。
不貞行為自体は否認しているものの、裁判実務では、性交渉があったものと推認されやすい事から、
不利な状態と言えるかと思われます。
これに対し、当方は、別居前から、相手方による多額の使途不明金の存在を主張し、
通帳等からその説明を求め、その説明内容に合理性がない事を主張しました。
最終的には、上記の通り、当方の考える財産分与の金額に30万円程度上乗せした解決金を支払う形で
裁判上の和解離婚を成立させることができました。
不貞行為の認定がなされた場合、有責配偶者という事になり、
有責配偶者からの離婚請求として、離婚が認められるには、7~10年程度は別居期間が必要となり、
その間、婚姻費用(生活費)を払い続けなければならなくなります。
従って、有責配偶者からの離婚請求の場合、早期に離婚を成立させることで、7~10年分の婚姻費用の支払を免れることが
できる事から、和解としては、離婚慰謝料(150~200万円程度)とは別に、婚姻費用の7~10年分程度の支払をして和解離婚を成立させるという事もあるところですが、
本件では、上記の通り、こちらの考える財産分与の金額に30万円程度上乗せした金額で(従って、早期離婚成立のための解決金としては30万円と考えることができます。)、
和解離婚を成立させることができ、大幅に離婚成立のための解決金額の低減を図ることができたと考えることができます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。

裁判所が用いるいわゆる、婚姻費用・養育費の算定表上で導かれる金額より、
月5万円、少ない金額を支払う形で婚姻費用分担調停が成立しました。
本件では、夫婦共に給与収入があり、離婚までの間の別居中の生活費である
婚姻費用の権利者である相手方が居住する自宅について、夫婦共に連帯債務を負っており、夫婦それぞれが
住宅ローンを負担しているという事情が存在しました。
婚姻費用の支払義務者となる当方の手取り収入から考えると、当方負担部分の住宅ローンに加えて、
算定表通りの婚姻費用を月々支払うとなると、当方の生活が立ちゆかなくなる、という現実的な問題が生じることを
手取り収入の資料及び月々の生活費等を具体的に示す形で、相手方の理解を求める事とし、
結果、算定表上の金額よりも月5万円少ない金額で婚姻費用分担調停を成立させることができました。
離婚までの間の当面の生活費である婚姻費用を定めるに当たっては、
婚姻費用の権利者が住んでいる住居の住宅ローンを、婚姻費用の義務者が負担している場合の調整が問題となります。
この点は、住宅ローンは、元来、不動産の所有者が自己の財産に費用をかけているに過ぎないことから、
住宅ローン額そのものを婚姻費用額から差し引くことはできないと考えられています。
もっとも、住宅ローンを支払っていることで、婚姻費用の権利者の居住費が浮いているという問題があり、
算定表に折り込み済みである、権利者の年収に対応した統計上の標準的な居住関係費(例えば、年収200万円未満の方であれば2万2247円程度)を
差し引くことが出来ると考えるのが一般的です(ただし、必ず差し引かれるという訳ではなく、別居の原因が、婚姻費用の義務者の不貞行為や暴力等にあるという場合、
差し引かない考え方が有力です。)。
本件では、婚姻費用の権利者のみならず義務者も自ら住宅ローンを負担しており、しかも、その額が、義務者の収入に対応した標準的な住居関係費を
超えている事から、別途、算定表上の婚姻費用月額から住居費を差し引く事ができないのではないか、という問題がありました。
そこで、今後の一家全体の生活を維持するためには、当方の手取り収入及び月々の生活費からすると、住宅ローンを払いながら支払える婚姻費用にも限界がある点を
資料に基づき説明し、相手方に理解を求める形で譲歩を引き出し、算定表上の婚姻費用月額よりも5万円少ない金額での婚姻費用分担調停を成立させることが
できました。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。