兵庫県姫路市の離婚法律相談所 | 離婚問題・離婚相談は、弁護士がお答えする城陽法律事務所へ
ご予約・お問い合わせはこちら
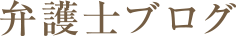
大学進学費用と養育費の終期について
お子様がいる場合、離婚時に養育費の取り決めを行うことが多いですが、
しばしば問題となるのは、①大学進学費用の取り扱い、②養育費の終期を何歳までとするかの点です。
①大学進学費用については、大学進学を了承していたか否かや、夫婦双方の学歴、収入等により個別に
検討します。ただし、大学進学を了承していた場合でも、夫婦の収入等によっては、国立大学の標準学費を基礎として、
算定表で考慮済みである公立高校の年間標準額費を超えた部分について、収入割合で按分するとか、奨学金の全部または一部を考慮し、 ...
婚姻費用、養育費の算定表の見直しについて
別居中の離婚成立までの間の生活費である婚姻費用や、離婚後の養育費について、
いわゆる「算定表」にもとづき金額の算定がなされているところ、
既に新聞報道がなされているとおり、この度、最高裁が算定表の見直しを
行うこととなりました。
見直しの発表は、令和元年12月23日の予定とされており、最高裁のホームページや公刊物なので
公表される予定です。
現在、婚姻費用や離婚、養育費の調停、審判が裁判所に係属している案件では、
裁判所は、婚姻費用、養育費の算定表の見 ...
離婚原因「悪意の遺棄」について
夫婦が離婚に合意すれば離婚できるのはもちろんの事ですが、
合意できない場合でも、法律上の離婚原因があると認定されると、
訴訟において、判決で離婚が裁判所により認められます。
法律上の離婚原因の1つとして、民法770条1項2号は、
「悪意の遺棄」を定めています。
時々、相手方が別居を一方的に行った上、生活費を負担してくれなくなったから悪意の遺棄に当たるのではないか?
との質問をお受けすることがあります。
「悪意の遺棄」とは、正当な理由のない ...
離婚時の財産分与でよくある誤解2
離婚の際には、財産分与について取り決めを行うことが多く、
離婚の条件として財産分与が整わないと離婚自体も成立させないという事が多いことから、
離婚自体に争いがないケースにおいては、一番大きな争点となることが多いです。
財産分与でよくある誤解として、「財産分与は、夫婦の実質的共有財産を対象として
価値を算定する」との文脈の理解が挙げられます。
時々、「まだ離婚が成立していないにもかかわらず、名義が相手方であることをいいことに、
夫婦の実質的共有財産である○○を勝手に ...
離婚時の財産分与の対象とならないと考えられる財産
離婚時には、財産分与についても取り決めを行うのが一般的です。
この点、株式については離婚の際の財産分与の対象となり、公開株式については
市場価格で価値を決め、非公開株式については、評価の方法が複数あり得るところですが、
会社の規模、性質、財産、収入等に応じて適切な評価の方法を選択することとなります。
それでは、医療法人の持ち分についてはどうでしょうか。
この点、平成18年の医療法改正後に設立された医療法人の場合、剰余金の分配のみならず、
解散時の残余 ...
別居期間が長いと、必ず離婚できるのか?
離婚について、双方が合意できない場合、離婚訴訟では、
法律上の離婚原因である、「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在するか否かを
裁判所が判断することとなります。
この点、不貞行為や暴力などの明確な離婚原因がない場合に、
主張されるのが、別居期間です。
単身赴任等の事情を除いた別居期間がある程度の期間(具体的には相手方の落ち度の有無程度により、3~5年程度)
になっている場合、夫婦関係が破綻しているのか否かの一応の物差しになるとの見方は実務でも
なされて ...
性交渉の拒絶と離婚原因
離婚を求めたところ、相手方がこれを拒絶する場合、
離婚訴訟では、一方が離婚を望まない場合でも離婚を余儀なくされる事情、すなわち、
法律上の離婚原因があるか否かが審理されることとなります。
それでは、夫婦間で一方が性交渉を拒絶し続けているという場合、
民法770条1項5号に言う、「婚姻を継続し難い重大な事由」の離婚原因があると
言えるのでしょうか。
この点、性交渉の拒絶と言っても、ケースは様々であり、
体調その他の健康上の理由で拒絶したとい ...
離婚時の財産分与と住宅ローンの処理に関する裁判所の考え方の変化
離婚を成立させる際に、合わせて財産分与の取り決めを行うことが多いことは、
みな様もご存じの事かと思います。
この離婚の際の財産分与は、基本的には夫婦の財産の名義の如何を問わず(婚姻前からの金額や親から相続した財産などは除きます。)、
基準時(通常は別居開始時または離婚調停申立時)にある全ての財産を合算して、
原則、半分ずつ分ける(2分の1ルール)というのが基本となります。
それでは、住宅ローンがある場合の離婚時の財産分与の処理はどのようになるのでしょうか。 ...
親権者の変更について
離婚の際に、子がいる場合、親権者の取り決めをしなければ
離婚を成立させることができない事は、ある程度広く知られているのではないかと
思われます。
離婚の際に一旦、親権者の取り決めを行った後、親権者ではない親が
離婚後に、親権者の変更を申し立てることがあります。
では、離婚の際に親権者をどちらにするかで争いがある場合に、
用いられる基準と、離婚時に一旦、親権者を取り決めた後に親権者を変更するか否かで争いがある場合に
用いられる基準では違いが ...
離婚が成立するまでの間の子の監護について
離婚を成立させるには、子がいる場合、子の親権を定めることが必要です。
このため、親権に争いがある場合、この点を調整しなければ、協議離婚、調停離婚が成立
しないこととなります。
例えば、相手方に不貞行為や暴力など、明白な離婚原因があり、これが立証できるという場合には、
離婚調停を不成立で終わらせた上で、離婚訴訟を起こし、判決で親権についても裁判官に決めてもらうことが
可能となります。
対して、このような明白な離婚原因の立証ができない場合、離婚調停を不成 ...